
話し手 読売新聞東京本社 編集局解説部 次長
南 砂 氏
聞き手 医療経済研究機構 専務理事 岡部陽二
厚生労働省は五年に一度、終末期医療に関する調査を行なっています。その第3回調査にもとづいて、昨年の7月には「終末期医療に関する調査等検討会」が報告書をまとめました。その報告書によると、たとえば終末期を過ごしたい場所の選択として一般国民は病院を第一に挙げているに対し、医師や看護職員は自宅を希望しているなどの意識の違いが明らかにされています。
この報告書をもとに議論が重ねられて、終末期医療の充実に向けた多くの提言がなされております。今回は、この「終末期医療に関する調査等検討会」の委員を務められました読売新聞東京本社編集局解説部次長南砂氏を迎えて、「終末期医療について」お伺いしました。
岡部 南さんは、ジャーナリストとしてご活躍されておられますが、もともとは医師で、ベルギーに留学された経歴もお持ちとお聞きしております。まず、南さんのご経歴とこの仕事を始められたきっかけをお聞かせください。
南 医学部の学生時代は、特別に興味のある臨床分野が見つからず、WHOのような世界的な医療行政、保健政策の仕事に携わりたいと思い、国際会議で通訳の助手をしたり、英語の勉強をしたりしていました。ただ、英語を勉強したくらいでは、WHOのような国際機関ではとても通用しないと思い、医師免許をとったあと、当時は治安がよく、“多言語”国であるベルギーに留学しました。
ベルギーでは、社会医学とフランス語を勉強しましたが、とくにベルギーの旧ベルギー領コンゴへの政策に興味を持ちました。当時のベルギーにはアフリカからの移民がたくさん来ており、その人たちが「カルチャー・ショック」などで、うつになったり、自殺したりすることが社会問題となっていたのです。
ベルギーで二年間ほど勉強して帰国し、大学の精神科で異文化との接触による精神保健の研究を始めました。当時、日本は統合失調症とうつ病が精神科の主流で、こうした分野は指導できる先生が少なかったのですが、幸いハワイ大学で日系移民の精神保健を研究してこられた江畑敬介先生にお目にかかる機会を得て、先生のご助言やご指導を頂くことができました。
1980年代の始めには、日本にもインドシナ難民が流入し、品川の八潮にベトナム人キャンプ、大和林間にはラオス人キャンプがあり、江畑先生が外務省の委嘱を受けて調査、診療される折に連れて行って頂いたりしました。私自身はその後、80年代半ば以後は、在日外国人留学生の相談に関わるようになりましたが、ある番組をたまたまお手伝いしたのがご縁で、1985年に読売新聞に就職させていただきました。
〇 終末期医療に関心を持ったきっかけ
岡部 本日は「終末期医療について」について論点を絞ってお話しをお伺いできればと思います。まず、終末期医療に関心を持たれたきっかけについてお聞かせください。
南 終末期医療の光と影の部分をもう少し丁寧に報道する必要性を感じたのがきっかけとなっています。医師が延命治療を中止したために、訴訟を起こされて医師が殺人罪に問われるといった事件が後を絶たず、終末期医療について国民に丁寧に説明することが必要ではないかと感じています。
このようなことが起こる理由の一つには、終末期医療について医療を行う側の裁量が十分に認められていないことが挙げられます。一般的に、日本の医師の裁量権は諸外国に比べ、幅広いと言われています。しかしながら、専門家としての医師の「裁量」は全く尊重されていません。特に、昨今の医療不信の高まりからそれは、無理もないことかも知れませんが、医師の「裁量」が尊重されていない現状では、延命治療に関する問題はなくならないと思います。
その背景として、日本では、医師の強制参加の職能団体はなく、医師免許の剥奪権は厚生労働省側にあります。弁護士の場合の日本弁護士連合会のように職能団体にはありません。こういう現状では、終末期医療の充実に法的な整備を行う必要性があると感じています。
〇 終の棲家はどこがよいか
岡部 日本には、「親を病院にも入れないで死なせたのか」という、国民感情があるのは事実のようです。文化が違うと言ってしまえば、それまでなのですが、英国をはじめ欧州諸国のターミナルケアは、「生活の一部を支援する」ということがかなり行われています。
南 確かに、欧米諸国に比べて、わが国の終末期医療が特殊であるというのは、おっしゃるとおりだと思います。その是非は別として、興味深いのは、ほんの三十年くらい前には10%に満たなかった医療施設での死亡が、最近では80%を超えました。
つまり、わが国でも、もともと終末期は医療ではありませんでした。それが全く逆になったということで、医療の恩恵が終末期にまで行き渡ったという見方もできます。そうすると、仮に、終末期を病院で迎えられないと、平均的な終末期を迎えられなかったような印象を持ってしまいます。つまり、自然な死に方ができなくなったと見るか、終末期にまで医療が行き渡ったとみるかで、見方が全然違ってしまいます。
岡部 南さんが関わられた委員会の「終末期医療に関する調査等検討会」報告書では、医師や看護職員に対しても、どこで死にたいか、自分に対する延命治療を続けてほしいかどうかアンケートをしていますね。
南 検討会では、五年ぶりに行われた第三回目の調査結果にもとづき報告書をまとめました。その中で、「高齢となり、脳血管障害や痴呆等によって日常生活が困難となり、さらに治る見込みのない状態の場合、どこで療養したいか」という調査項目がありまして、およそ四割から五割の医療従事者が「最期まで自宅で療養したい」と答えています(表1)。
一方、一般国民の希望としては、終の棲家は自宅ではないかと思っていましたが、「最期まで在宅」を希望したのは二割で、むしろ病院を望んでいました(表2)。これを受けて、医療関係の新聞などが、「在宅希望は二割」とセンセーショナルに報道したのですが、実は、この調査を丁寧に分析すると、そうではないということが分かります。
質問項目をみると「高齢となり、脳血管障害や痴呆等によって日常生活が困難となり、さらに治る見込みのない状態の場合、どこで療養したいか」と聞いており、在宅医療の整っていない現状では在宅は無理だろうという気持ちが働くのではないかと分析できるのです。
つまり、「条件さえ整えば、住み慣れたところにいたいと思う」人が多いであろうことが、丁寧に分析すると分かります。やはり国民の多くは、住み慣れたところで療養したく、できることならば、「管につながれたりはしたくない」というのが、国民感情であろうと思います。
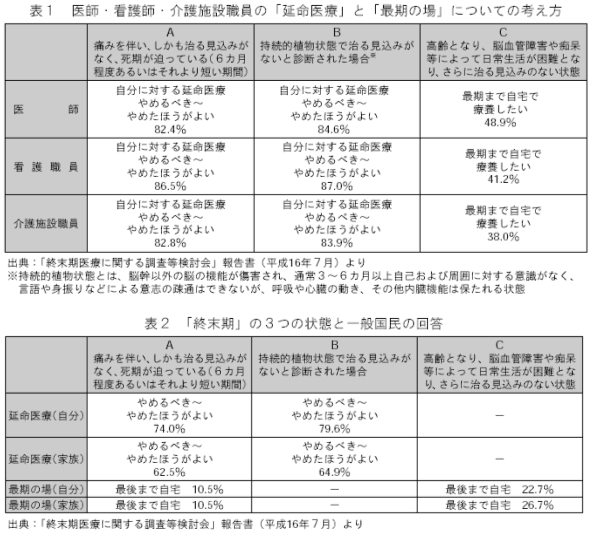
〇 疼痛緩和
岡部 疼痛緩和に使用されるモルヒネの使用量の国際比較をみると英国84(g/100万人)、オーストラリア83、米国52、フランス32に比べて、日本の使用量は8.3と極端に少なく、積極的に疼痛緩和が行われていないのではと言われています。つまり、わが国の終末期医療においては疼痛緩和という視点が希薄なのでしょうか。
南 WHOが、医療上、必要性が認められる患者への積極的な使用を勧告しているのにもかかわらず、モルヒネによる疼痛緩和はわが国ではあまり積極的に行われていません。この現状は、モルヒネに対するアレルギーがまだ残っていて、使用量を抑える傾向があると思われます。それに加えて、麻薬取締法の規制が非常に厳しく、モルヒネの管理や使用について厳しく規制されています。したがって、個人開業の医師が在宅診療でモルヒネを使うには、非常に手続きが煩雑なため、運用上使いにくい現状もあるようです。
岡部 現状では、医師はモルヒネを使いたいけれども手続きが煩雑で、しかも、使用法の教育も十分にできていないという状況でしょうか。この問題は、医学部での教育の問題にも発展する問題ですね。
〇 ホスピス、高齢者介護施設(特養、老健)での看取りの問題
岡部 わが国におけるホスピスの状況をみると、140施設、2,645病床(申請準備中70病棟)と五年前の30病棟から急速に増えてきました(2005年2月現在)。しかしながら、欧米と比較すると、米国は2,100(在宅プログラムを含む)、英国は203施設、3,110病床(1994年)で、わが国のホスピス数は欧米に比べてまだまだ少ない状況です。しかも、わが国のホスピスの多くは病院に併設されており、独立したホスピスの多い欧米諸国とは状況が異なります。どのようなホスピス充実策を採るべきとお考えでしょうか。
南 わが国のホスピスは主にがん患者が中心ですが、諸外国ではがん患者に限らず、他の病気での終末期の患者も入院しています。わが国の場合、まだまだホスピスが非常に少ないので、どうしてもがんの末期患者しか恩恵を被れないような状況です。しかも、がんで年間約30万人死亡しますが、そのうち、ホスピスで亡くなる方は、ほんの数パーセントです。
岡部 つまり、ホスピスの絶対数が少ないということですね。
南 そうです。スウェーデンの場合、がんで亡くなる人の30%がホスピスで亡くなっており、関係者はわが国でもせめて10%台にしたいと主張しています。しかし、わが国では単独型のホスピスではとても採算が合わず、結果として病院併設型のホスピスが多くなります。
また、病院併設型でもホスピスは不採算部門として位置づけられ、積極的には展開されていないのが現状です。前回の診療報酬改定で多少改善されましたが、依然、収益面において採算が合っていない現状があるようです。やはり、政策的に経済的な動機づけをすることが、ホスピスの普及を促進する重要な点だと思います。
岡部 在宅ケアの充実もホスピスの効率を上げるためには重要な視点と思います。先日、米国ポートランドのホスピスを見学したところ、そのホスピスは20床で、看護師など200人、医師2人のスタッフで約2,000人の終末期ケアをしていました。要するに在宅ケアが非常に充実していて、どうしても入院が必要な患者だけを入院させているようです。
わが国でのホスピスの普及という点を考えると、ホスピスを特別養護老人ホーム(以下、特養)や老人保健施設(以下、老健)の一部と位置づけるべきではという意見もあるようです。この点に関してはどうお考えでしょうか。
南 この問題の原点はそもそも終末期の定義が今まではっきりとしていなかったところにあります。過去二回の調査においては、終末期医療の意識を問う際に、「植物状態になった場合」と「がんの末期」の二つに限っていましたが、昨年行なわれた三回目の調査で初めて、「老衰や痴呆のように長い期間療養を経て亡くなる場合」が追加されました。
実は、「老衰や痴呆のように長い期間療養を経て亡くなる場合」の方のほうが、がん患者より圧倒的に多い訳で、この状態の終末期をどう考えるかという視点が非常に重要です。このような状態を考慮に入れると、特養や老健とホスピスがかなり近づいてくると思われます。
岡部 慶應義塾大学の池上教授は、終末期ケアを考えるにあたり、医療に加えて介護も必要になる場合が多いことから、介護保険法の中に「終末期ケアへの対応」を明記するように改めるべきであるとお考えのようですね。
南 確かにそうだと思います。老衰や認知症の方の終末期が問題になると、当然のことながら施設での看取りが、今後、議論されるでしょう。今回の調査では、「高齢化の進展に伴い、介護老人福祉施設で最期を迎える人が増えてきたため、介護施設職員も対象に加えた」としていますが、これについて「特養や老健などでの看取りが増えている現実はない」と日本福祉大学教授二木立氏は指摘しておられます。
今後、がんや特別の病気ではなく老衰や認知症などで終末期を迎える高齢者が爆発的に増えることを考えれば、高齢者施設での看取りの問題をきちんと議論することが必要です。
結局は、終末期への対応のあり方についてまだ十分に議論できていないのが現状だと思います。マスコミも非常に不勉強だと思うのですが、たとえば、北欧には、寝たきりの人がいないといったいわゆる「北欧神話」は、マスコミを通じて国民の意識に染みついています。
しかし、観点を変えると、スウェーデンでは、そこまでは医療はやらないという見方もできるわけで、さらに終末期において「延命治療を始めない」ということと「中断する」ということは、法律的に決定的に意味が違うのにもかかわらず、国民はもとより医療現場でも、この点が整理できていないということも今回の報告書に明記され、医療者のためのガイドラインの整理などが必要、とされました。
岡部 そういった問題でコンセンサスを得るのは、現状ではなかなか難しいでしょうね。
南 難しい問題ではありますが、普通の高齢者の死が今後増えていくということから考えると、国民のコンセンサスを得て、医療の環境を整備していくべきだと思いますし、そのような時期に来ています。マスコミも諸外国の事情を紹介する際に丁寧に伝え、わが国ではどのような形が望ましいかというところまで議論しないと、十分とはいえないでしょう。
岡部 内容的には進んでいる英国や北欧のホスピスがそのままわが国に当てはまるかというと、そうではないということですね。
南 そう思います。いいか悪いかは別として、これだけの人が病院で医療の手で亡くなるようになった現在、医療を受けないで亡くなるということに対して、国民が納得するかどうかです。
英国や北欧などで受け入れられているナーシングホームでの看取り、つまり医師でない人によって、死が確認されるということを国民の過半数が認めるようになれば、特養や老健で看取るべきか否かという議論になるでしょうが、現状は違います。医療を全く受けることなく、特養や老健で最期を看取られる、ということでよいのかどうか、コンセンサスを得なければならないでしょう。
私の考えでは、全く医師の手を離れて特養や老健のような介護施設で最期を迎えると言うことでなく、ある程度、介護と医療の両方の恩恵が受けられるというのが、国民の多くが望む最期ではないかと思います。
〇 終末期医療における精神面・生活面でのケア
岡部 英米ではホスピスに最低一人の精神科医と牧師が勤務していますが、わが国では精神面・生活面でのケアが十分でないという指摘もされています。
南 高齢者の精神面・生活面のケアの充実を図るには、子どもの場合の「小児科」にあたる本当の意味での「老年医学」の充実が不可欠だと思います。小児というのは、大人のミニュチュアではないということで、小児科があるわけです。高齢者も同様に、普通の成人とは違う特殊性があるという前提で、老年医学があります。つまり、歳をとると、病気の起こり方や悪くなり方などが普通の成人とは違うという考え方です。また、「加齢」というのはどういうことかということを極める学問です。
しかしながら、わが国では老年医学という分野は、まだ十分に確立されていません。十年程前に、いろいろな大学病院で老人病科などができたのですが、いざ蓋を開けてみると、心臓専門家は、「心臓病」を糖尿病専門家は「糖尿病」を診療しているに過ぎないということになり、結局、成人向けの普通の科と変わりがなく、老人病科を閉めた大学も多くあると聞いています。
老年医学とは、「加齢」がもたらす身心のメカニズムが主体であり、精神医療はその多くの部分を占めるでしょうし、アルツハイマーも大きなテーマです。繰り返しになりますが、普通の高齢者の死が今後増えていくということから考えると、一層の老年医学の充実が必要になります。
終末期医療の意味は、高齢者のQOLを向上させることであって、QOLを向上するということは、命を救い、病気を治すだけではありません。その本人が、十分に満ち足りた気分で暮らすことが重要なのです。そういった意味からも、地域医療の中で高齢者を診ることができる総合診療医の育成も必要となってくるでしょう。
〇 リビング・ウィル
岡部 次に、リビング・ウィルについてお伺いします。尊厳死協会の会員数は10万人を超え、尊厳死を実践する「リビング・ウィル」の考え方は徐々に国民にも医療現場にも受け入れられつつあるようです。一方で治療中止のタイミングや健康なときに意思表示があったとしても、終末期に同じ気持ちでいられるかいった問題も指摘されており、解決しなければならない点も多くあると思われます。
南 おっしゃるとおり、高齢になるほど「本人の意思」というのが確認しづらくなります。では、誰かが本人の意思を尊重して、代わって表明できるかというと、今後の家族制度などを考慮すると、非常に難しい問題です。ドイツなどは、「医療の代理人」という制度が、きちん法律になっています。わが国でも、自分の最終的な意思表明の代理してくれるような人が必要となってきます。たとえば、法的な後見人でもよいし、かかりつけの医師が代理人を勤めてもよいと思います。
岡部 医療の代理人という枠組みを、リビング・ウィルの中に入れてしまえばよいわけですね。
南 そうですね。今回の調査で興味深いのは、リビング・ウィルを法制化するということに対しては、国民の賛成が前回より少し減ったことです。一方で、リビング・ウィルという考え方を認めるという方は過半数になりました。おそらく、リビング・ウィルを法律にしてしまうと、若い時に「もしこうなったら、私は延命医療を放棄します」と書いてしまうと、一律的に扱われるのがいやだという印象を、国民は持ったのではと思われます。
歳をとった時の価値観と若い時の価値観とは違うということを前提にリビング・ウィルという制度を確立しなければならないということです。
つまり、高齢になればなるほど「死にたい、家に帰りたい」などと言う人がいます。それをどう読むかだと思います。このようなことに慣れた医師であれば、それを額面どおりには受け取らないでしょう。
岡部 わが国でもリビング・ウィルは法制化するという方向に動くのでしょうか。
南 そうなる可能性はあるでしょう。尊厳死協会の会員数が10万人会員を超えたということで、国会に請願を出していますので、いずれは議員立法で法制化されことも考えられます。どこまでを「自然な死」と考えるかを踏まえたうえで、制度を決めるということが重要です。
岡部 臓器移植法と同様に、あまりにがんじがらめにしてしまえば使い勝手が悪くなります。法制化することによって、逆に、リビング・ウィルの普及が進まなくなる懸念もあるので、十分な検討が必要ですね。お忙しいところ、ありがとうございました。今後のご活躍を期待しております。
(2005年4月発行、医療経済圏機構レター”Monthly IHEP"No.130,p1~7所収)
